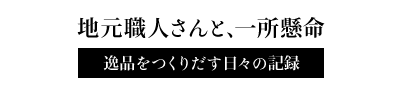大阪城と関わり深い小豆島の八人石のお話
こんにちは、スタッフ金井です!
醤油、佃煮、お素麺、オリーブ等の様々な産業が有名な小豆島。
「食」の魅力があふれる島という印象を持つ方も多いのではないのでしょうか。
しかし、小豆島の魅力ある産業は「食」以外にもあるんです!
その一つが石材業です。
小豆島では良質の花崗岩(小豆島石)が産出され、かつては大阪城の再建の際に数多くの小豆島石が海を渡り大阪まで運ばれました。
島内には昔から採石、加工、運搬などに携わる人が数多くあり、現在も加工品、港湾工事等で小豆島の石が活躍しています。
石材業は島を支える重要な産業なんです。

この小豆島での石材業は江戸時代初期から始まっており、石材業の跡が残る場所として、以前のブログでは「天狗岩」をご紹介しました。
天狗岩の話はこちらから!→豪雨で現れた天狗岩 – 小豆島せとうち感謝館
そこから車ですぐのところに、「八人石丁場」という、こちらも400年ほど前に作業されていた跡がそのまま残る場所があります。
なぜここの場所が「八人石丁場」という少し変わった名前なのかというと、、、
400年ほど前に起きたある出来事が由来となっています。

時は遡ること1620年、夏冬と二度におよぶ大坂の陣で破壊的な損傷を受けた大阪城は、大規模な改修に取り掛かっていました。
石垣を担当する藩は城主の威信をかけて、巨大な石を運び込むことを競い合っていました。
山の中腹にひときわ目立つ大きな岩を見つけたのは、黒田藩。
巨大な岩の上半分を巻くように3日がかりで金ノミという大型金槌を使って「矢穴」という細い溝を開けました。
すると、まだヒビは出ていないものの、もう一息で大きな四角い石が切り出せる見通しが着いたので、
石工たちは一度一休みをしました。
石工の中に、ケガで休んだ親の代わりに来ていた少年がおり、休憩中に父の回復を願って「般若心経」を小声でつぶやいていました。
途中でつっかえてしまったので目をつむったところ、岩の上からお経の続きが聞こえてきました。
「おやっ、誰か上に人がいるのか」と少年が岩の横を上りかけたその時、
突然、「バリバリッ!」と言う音と「ズズズンッ」と突き上げるような地響きが続き、
休憩中で下に座っている八人の石工たちの上に切り出そうとしていた大岩が横倒しに倒れ込んだのです。。。
余りにも巨大な岩であるために、掘り起こそうにも岩が沈み、引きずって動かすこともできませんでした。
岩はそのまま置かれて石工八人の墓標となったまま、400年後の今まで残されているのです。
岩の前には慰霊碑が建てられています。

今も岩の下に人がいるのか⁈と驚きますが、みなさんも実際に訪れてみると、自然に出来た巨大な岩に圧倒されるはずです!