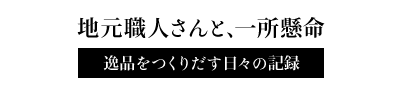小豆島醤油を支える「木桶」
こんにちは、スタッフ金田です☀
風が涼しく、少しずつ秋を感じられるようになってきましたね。食卓に並ぶごはんやおかずも、どこかほっとする味わいを求めたくなります。私はこの時期になると、小学生のころにおじいちゃんが庭先でキノコやカボチャを焼いてくれて、島の醤油をかけて食べていたのを思い出します。
その時小学生だった私は、おじいちゃんが、お友達の作っている小豆島醤油を「この醤油めっちゃおいしいやろ」と何度も自慢していたのを聞き流していました。
しかし、今でも不思議とその味だけはしっかり覚えているんです(^^)そんな美味しい小豆島の醤油づくりを支えてきたのが「木桶」。今回は、その木桶についてお話ししたいと思います!
木桶には乳酸菌などの微生物がすみつき、独自の発酵生態系を作ります。この微生物たちの力によって、木桶醤油ならではの複雑で奥深い味わいが生まれます。何十年、何百年と使われ続けてきた桶だからこそ、そこに住む微生物たちが生き続けているのです。


▲ずっと醤油づくりに使っている木桶の表面▲
実は、小豆島は面積わずか約153㎢の小さな島ですが、全国で最も多い、1,000本以上の木桶を有しているんです! 桶屋曰く「全国にある木桶の1/3以上が小豆島にある」そうなんです。400年ある小豆島の醤油づくりの歴史の中で、今でも木桶を使った醤油づくりを守り続けています。ところが――この醤油づくりに大切な木桶が、いま危機に直面しています。
『『このままだと醤油につかう木桶を作れる人がいなくなってしまう!』』
現在使われている木桶のほとんどは戦前に作られたものなんだそうです。木桶は100-150年もの間、醤油屋さんで使われるため、ここ何十年も新しい木桶の導入はほとんどありませんでした。そのため、醸造用の木桶を製造する桶屋さんがなくなってきています。
「木桶は生きていて呼吸している」と、お醤油屋さんは話されます。まさにその通りで、木桶が生きているからこそ、いつまで美味しい醤油を作れるのかは誰にもわかりません。100年、150年経ったからそろそろ替えよう、という目安はなく、ある日突然、醤油が漏れてしまうなど、木桶の限界がやってきて初めて買い替えが必要になるのです。

▲もともと100年使っていた木桶があった場所。醤油が漏れ出たためやむを得ず取り壊されました▲
木桶職人がいなくなっている今、小豆島の木桶醤油は危機的状況なのです。
次のブログでは、そんな状況を救うべく、醤油職人が始めた「木桶職人復活プロジェクト」についてご紹介します。お楽しみに!
▼YouTubeで醤油職人が木桶醤油の魅力を発信しています。下の画像をクリック!▼