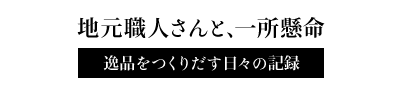1年に1度の、神聖な場所
こんにちは、スタッフ金田です。
10月の小豆島はお祭り1色!島の各地域が活気づいています!
小豆島のお祭りの歴史はこちらをご覧ください▶▶▶小豆島 秋の太鼓祭り
今日は小豆島の太鼓祭りの中でも、私たち「小豆島せとうち感謝館」スタッフも参加した“亀山八幡宮 例大祭”についてお話しします(^^
お祭り当日、担ぎ手や乗り子たちの朝は早い時間から始まります。お祭りが行われる八幡さんまで地区の太鼓を押して向かい、道中では元気な掛け声や音頭でとても賑やかです。中には、海辺の地区から太鼓を押してくるところもあり、海の中から太鼓とともに姿を現すその光景はまさに圧巻です!海から太鼓が陸に上がると、ほかの地区の太鼓もどんどん会場へやってきます。こうして、地区ごとの太鼓が八幡さんへと集まり、お祭り会場は盛り上がり始めます!
参加地区の太鼓が集まると、まずは八幡さんの境内でそれぞれが太鼓の奉納を行います。地区ごとに担ぎ手の“はっぴ”のデザインや掛け声、太鼓のたたき方が異なり、地域ごとの特色を楽しむことができます(^^

全地区の奉納が終わると、各太鼓は八幡さんの下にある広場に集まります。この広場では集団演舞のように太鼓台3~4台ずつが、高く持ち上げたり、担ぎ上げながら会場内を回ったりして、力自慢を競います。地域の人は、「池田(※池田地区)の桟敷(さじき)」からお祭りを見下ろすことができます。この桟敷は高さは18メートル、全体の長さは80メートルもあるんです!急傾斜を利用して石垣を築き、数段の平地を形作っている“国指定重要有形民俗文化財”です。江戸時代の亀山八幡宮の祭礼を描いた文化9年(1812)の奉納絵額には、桟敷に小屋を建て、太鼓台などを見物している人々が描かれているんですよ(^▽^

この「池田の桟敷」は1年にたった1度の、このお祭りの日でしか使われていない神聖な場所なんです。人々が集う広場であることが評価され、昭和45年(1970)の大阪万博のメイン会場である「お祭り広場」のモチーフにもなりました!

また、この亀山八幡宮の例大祭では太鼓台を横に倒す技も見ものです!人力で真横に太鼓を倒す姿には驚いてしまいます。((実はこの太鼓、地区にもよりますが1~2tもの重さがあるんです。
担ぎ手として参加した男性社員たちは、次の日の出勤で肩が痛くて上がらない!と嘆いていました(*_*;
来年のお祭りも皆で盛り上げていきたいと思います!